株式会社ベネクス
代表取締役 中村太一氏
コロナ禍を経て健康への意識がより高まるなか、“着て休むことでリカバリーする”という新しい発想で注目を集めるリカバリーウェア。そのパイオニアである株式会社ベネクスは、リカバリーウェアを18年間開発、製造、販売し、健康づくりの3要素のうち「休養」に着目した事業を展開しています。今回は、代表取締役の中村太一さんに、リカバリーウェア誕生の裏側や、リカバリーを取り巻く環境の変化について伺いました。
コロナ禍を経て健康への意識がより高まるなか、“着て休むことでリカバリーする”という新しい発想で注目を集めるリカバリーウェア。そのパイオニアである株式会社ベネクスは、リカバリーウェアを18年間開発、製造、販売し、健康づくりの3要素のうち「休養」に着目した事業を展開しています。今回は、代表取締役の中村太一さんに、リカバリーウェア誕生の裏側や、リカバリーを取り巻く環境の変化について伺いました。
― 9月30日で創業20周年を迎えられたとのこと、おめでとうございます。まずは、20年を振り返ってみていかがですか。
中村:ありがとうございます。20周年と言われて、もう20年経ったのかというのが正直な感想です。これまでずっと未来を見て進み続けていたら20年が経っていました。いつの間にか20年が経っていました。良い商品をお届けできているという自信があり、その結果として『リカバリーウェア』という言葉の認知度が上がっていることを大変うれしく思います。
― 昨今話題となっているリカバリーウェアですが、最初に開発したのがベネクスさんということで、開発に至った経緯をお聞かせください。
中村:当社のモノづくりは、介護用の『床ずれ防止マットレス』の開発から始まりました。私が前職で介護施設の立ち上げに携わっていた際に課題だと感じていたことの一つに、寝たきりの高齢者に多い「床ずれ」問題がありました。その原因を調べていくなかで、血行の滞りが一因であること、さらに掘り下げると体のオン・オフを切り替えるスイッチのような役割を持つ自律神経の働きが大きく影響していることを知りました。そこで、マットレスの表面に機能性のある素材を使うことで根本的な解決が図れないかと考え、開発を始めたのです。
しかし、前例がないなかで素材開発は苦戦し、さらに繊維に練り込む難しさにも直面しました。多くの困難を乗り越え、当社独自開発の特殊繊維「PHT(Platinum Harmonized Technology)」が完成したものの、マットレスは売れず、事業としては失敗に終わりました。その糸を活用して作ったのが、リカバリーウェアです。
― 前例のないことに諦めず挑戦した結果、リカバリーウェアが完成したのですね。当時の反応はいかがでしたか。
中村:ある展示会で、試作品のTシャツを「ケアウェア」として介護ヘルパーさん向けにご紹介していました。すると、偶然通りかかった大手ジムのバイヤーさんが可能性を感じてくださり、「日々体に気を遣うトレーニーに良いのでは」と、テスト的に販売していただけることになったのです。これが大変好評で、瞬く間に口コミで広がりました。そこから、アスリートや一般の方などより多くの方に使っていただきたいと考え、「リカバリーウェア」に商品名を変更し、本格的に販売を始めました。
当初は「着るものでリカバリーする」という概念がなく、「リカバリー」と聞けばパソコンの修理をイメージされることがほとんどでした。これが画期的なアイデアと評価され、2013年にはドイツで行われた世界最大級のスポーツ見本市「ISPO」で日本企業初の金賞を受賞しました。今では、休養や疲労回復といった意味で定着してきていることに感動を覚えます。
― まさに新たな価値を生み出したのですね。VENEXリカバリーウェアの要となっている技術は「PHT繊維」だと思いますが、この素材には、どのようなこだわりや技術が詰まっているのでしょうか。
中村:PHT繊維は、ナノプラチナなどの数種類の鉱物を繊維一本一本に練り込んだ、当社独自の素材です。私たちは、このPHT繊維が身に着ける方の体温に反応して発する、身体に優しく働きかける特性に着目しました。このPHT繊維がもたらす心地よい環境が、心身が安らぐリラックスタイムをサポートし、質の高い休養につながると私たちは考えています。創業以来、国内外の19の大学などと連携しながら「休養」を科学的に研究し、お客様が心から安らげるためのモノづくりを追求しています。
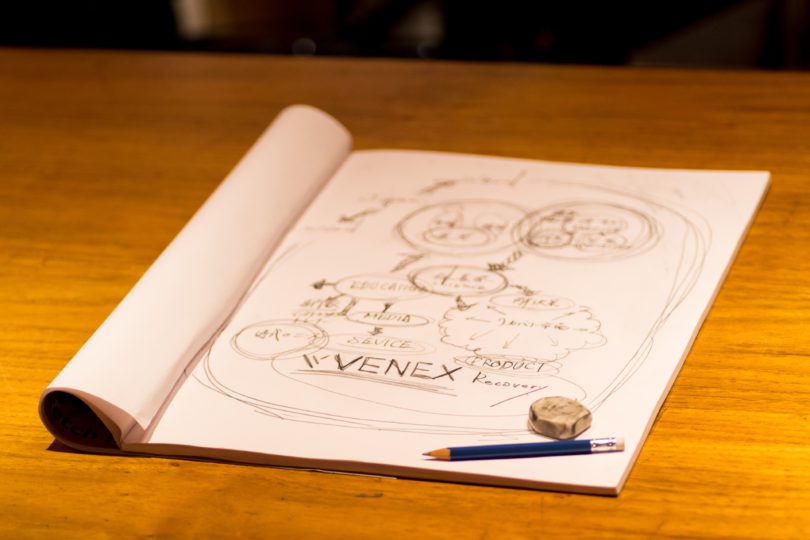
― 近年「リカバリーウェア」が注目されていますが、中村さんから見て、今のリカバリーウェア市場の成長をどう感じていますか。
中村:当社は創業当初より「世界のリカバリー市場を創造し、そこに関わるすべての人を元気にする」というビジョンを掲げ、まずは市場そのものをつくることを目指してきました。近年、参入企業様が増えてきたことで、その市場がやっと形になってきたと感じています。それに付随して、一般医療機器にリカバリーウェアのカテゴリーが新設されたことも大きな出来事でした。法整備がなされたことで、より市場としての形が整ってきたと思います。
― 一般医療機器とリカバリーウェアの関係について教えてください。
中村:当社が世界で初めてリカバリーウェアを開発し、実験でもお客様の使用感でも効果が確認できましたが、当時は販売や安全管理に関する基準がありませんでした。どのような制度に則れば良いのか分からず、市場を形成するには高いハードルがありました。そこで注目していたのが一般医療機器です。しかし、当時はリカバリーウェアが当てはまるカテゴリーがなく、悔しい思いをしていました。その後、多くの企業様が市場に参入してくださったおかげで、2022年に厚生労働省によって一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」というカテゴリーが新設されました。新カテゴリーができたのはなんと約42年ぶりで、これが市場成長の大きなカギになったと考えています。
― 市場における御社の役割をどのように考えられていますか。
中村:市場が活況となることはとても良いことですが、その一方で、市場を健全に成長させていくためには、業界全体の信頼を損なわないようルールを遵守することが不可欠です。リカバリーウェアのパイオニアとして、常に業界の適正化をリードできる存在でありたいと考えています。

― 創業当初、コロナ前、コロナ後、今と時代の変化とともに、ターゲット層やご購入者の層の変化が変わったことはありますか。
中村:創業当初は、日々トレーニングをされ、ご自身のコンディションを常に考えているアスリートといった、コアなユーザーさんが多かったですね。そこから、健康に対するリテラシーが高い経営者の方などが増えてきました。ご自身のパフォーマンスを高い状態で維持する必要性を感じ始めたのだと思います。さらにコロナ禍を経て、より良い生活や健康へと人々の意識が向き、ご自身の疲れに気づく方が増えました。これを機に、リカバリーウェアを多くの方に手に取っていただけるようになったと感じています。
― リカバリーウェアに対する期待について、始めた頃と今で変化はありますか。
中村:始めた頃は、「パジャマ」のような、時代に合った新しい商品カテゴリーを作りたいと思っていました。それは今、実現しつつあると感じています。一方で、今後それが文化として根付いていくかは、これからの私たちの展開次第です。「そういうのもあったよね」と一過性のトレンドで終わることは避けたいですね。私にとって「リカバリーウェア」は、非常に手軽で、毎日着られるものです。皆さんも毎日「着替える」ことはしますよね。せっかく着るなら機能性のある良いものを着てほしい、という想いで日々商品開発をしています。寝具に置き換えると、「毎日寝るなら良い枕やベッドが良い」という感覚と同じです。リカバリーウェアが生活の中に根付くためには、これまで以上にお客様にご満足いただけるモノづくりをしていかなければならないと思います。

【プロフィール】
株式会社ベネクス代表取締役 中村 太一氏
慶応義塾大学商学部卒業後、コンサルティング会社に入社。同社の運営する有料老人ホームの立ち上げ、営業を経て、2005年9月、株式会社ベネクスを設立。東海大学や神奈川県との産学公連携事業により休養時専用のリカバリーウェアを開発し、国内のみならず海外にも展開している。次の時代を担う創造企業の代表として、自ら行動・挑戦し続けている。
ベネクス公式ホームページ:https://www.venex-j.co.jp/