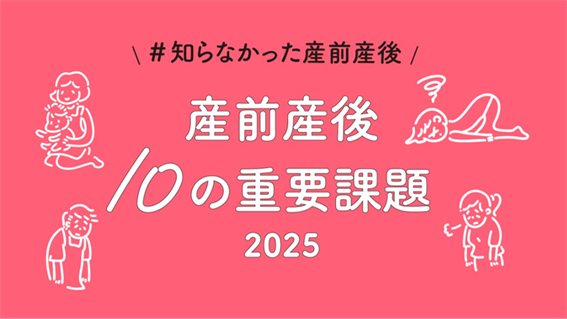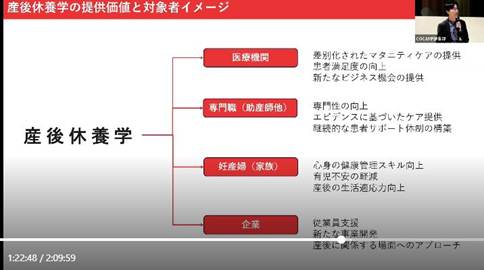2025年10月10日、「産後リカバリーの日」に合わせて開催された「産後リカバリーシンポジウム」では、産後女性の休養と回復に焦点を当てた議論が行われました。本シンポジウムは、2022年に発足した「産後リカバリープロジェクト」の一環として開催され、産後女性の心身のケアや社会的支援の在り方について、企業や専門家、行政など多方面の関係者が集まり意見を交わしました。
開会の挨拶を務めたのは、産後リカバリープロジェクトの主管企業である「大広フェムテックフェムケアラボ」の平野さん。同社は、フェムテック・フェムケア領域で活動する広告会社として、産後女性の休養支援を目的とした事業やサービスの創造に取り組んでいます。平野さんは、「産後の女性が必要な休養を取れる社会の実現を目指し、多くの企業や自治体と連携していきたい」と語りました。
続いて、プロジェクト事務局の柴田さんが、産後リカバリープロジェクトの設立経緯や目的について説明。同プロジェクトは、産後女性の心身の回復に必要な正しい知識を普及させるために立ち上げられ、現在は3期目を迎えています。柴田さんは、「産後の女性が十分に休養を取れない現状を変えるため、社会全体を巻き込んだ取り組みが必要です」と強調しました。